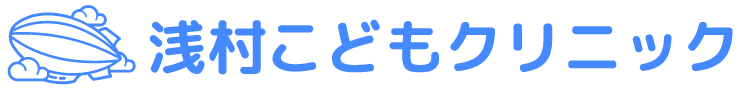学会ってなに?
院長が国際学会に参加してきました。「学会」…東京国際フォーラムなどの会議場で時々目にしたり、なんだかドラマに出てきそう、といった怪しい?響きがあります。実際のところ、「学会」とはどのようなものか、ごくごく簡単に解説します!
今回のブログで取り上げている「学会」は正式名称を「学術集会」「年次集会」などと言います。多くの学会は1年に1回開催されますが、1年に2回行われるものや、2年に1回の場合もあります。「国内学会」「国際学会」に分けられます。国内学会は日本小児科学会、日本てんかん学会などの日本国内の学会(この場合は学術集会ではなく、専門医の集まりの団体を示します)が主催し、国内各所で行われます。国際学会は日本を含む世界の学会が主催し、京都や東京など日本国内で行われる場合もありますが、多くは海外で開催されます。
国際学会の公用語は英語。発表、討論を全て英語で行います。必要とされるのは語学力よりも「自分の考えを伝えたい」と思う熱い気持ち。英語がヘタでも、passionがあれば必ず伝わります。
学会の発表は大きく分けて2つに分類されます。1つ目は「基調講演」「特別講演」「シンポジウム」などと呼ばれるもの。2つ目は「一般講演」。基調講演は、学会の分野のエキスパートとされる先生により、その領域の最新の研究成果、これまでの医学研究の歴史などについて全体的な内容の発表です。その領域に詳しくない先生でも、基調講演を聴講することにより、医学における現在の課題、展望について詳しくなれます。
一般講演は普段の診療や研究において見つけた新発見を参加者に広く公開します。病院に勤務している時には、日々の研究成果を学会で発表することが強く求められ、関連学会には毎年発表をしていました。一般的に「学会で発表する」とはこの一般講演を指すことが多いです。
発表内容は一般公開されないため、一部をぼやかしての投稿にはなりますが学会会場の雰囲気をお届けします。
|
|
|
|
|
|
|
|