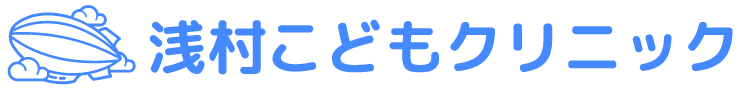こどものけいれん
しばらく小児科一般の話題が続きました。神経外来を訪れる患者さんが増えてきました。小児神経の領域は多種のお病気に対応しています。その中で多い相談が「ひきつけ」「けいれん」です。
けいれんを目撃したら
- まず始めに、落ち着いてください。口にタオルなどのものを入れたりしないでください。
- お子さんが自転車に乗っているなどしている場合は、速やかに安全な場所に移動しましょう。室内の場合は、椅子やソファなどからやわらかい床やベッドに移動させ、横にしてあげてください。
- けいれん(発作)の持続時間を測りましょう。「○分○秒」のように正確に測る必要はありません。「だいたい○分」程度で十分です。残念ながら、お薬を投与(注射または頬粘膜)する以外に、発作を止める方法はありません。自然に治まるのを待ちましょう。
- 余裕があれば、スマートフォンなどで発作の様子を動画に記録してください。頭から足まで全身が入るようにするとよいでしょう。
- 発作が5分以上続くとき、けいれんが終わっても呼びかけに反応しなかったりぼーっとしていて様子がおかしい時には救急車を呼びましょう。
けいれんの原因
けいれんの原因はたくさんあります。1回の発作だけでは診断に結びつかないことも多く、一方で発作が人生で1回だけということも少なくありません。今回は0歳から5歳、特に2歳くらいまでに多い「熱性発作」についてお話しします。
熱性発作(熱性けいれん)
当ブログで全てをお話ししたいのですが、とても足りません。わかりやすいサイトをいくつかご紹介します。
私から特にお伝えしたいことは下記のとおりです。
- 熱性発作を繰り返す確率は15-30%で、過半数のお子さんは発作を繰り返さない
- 一部のお子さんがてんかんに移行することがあるが、90%以上はてんかんを発症しない。てんかんを過度におそれる必要はない
- 発熱した時にダイアップ坐剤(R)を予防的に使うかどうかは、かかりつけの先生と相談。医師の指示に従いましょう
- 続いている発作を止めるにはダイアップの有効性は低い。ダイアップはあくまで予防のためのお薬
- 予防接種を控える必要はない。発作があっても速やかに接種を。最終的には接種する医師の判断になるため、発作からどれくらいの期間をあけたらよいかはかかりつけの先生と相談
熱性発作は過度の心配は不要、と申し上げましたがお子さんがひきつけを起こしているのを見るのは大変ご心配なことと思います。けいれんに限らず、お子さんの症状について気がかりなことがあれば、どうぞお気軽に当院までご相談ください。神経外来で丁寧にご説明します。